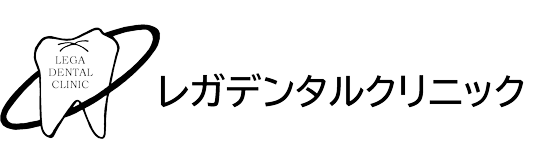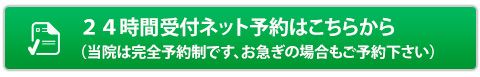歯のトラブルを引き起こすそもそもの原因は何か?
私は歯科治療の現場に立ち、毎日診療を続けています。もう30年以上になります。
たくさんの患者さんを診る中で、臨床から学んだ経験則が少しずつ増えてきました。
でも、それはあくまで私の経験則です。科学的に検証されたものではありません。一人で確かめるのは難しいのが現実です。
だからこそ、日々の経験に合う知見がないか、学会の論文をよく読んでいます。
今回、歯のトラブルの原因について、私の経験則を裏付ける興味深い論文を見つけました。ぜひご紹介したいと思います。
経験則:歯のトラブルになりやすい人は?
論文をご紹介する前に、私の何年にもわたる臨床から得られた経験則をお伝えします。「歯のいろいろなトラブルの原因は、歯をうまく磨けていないからだけではない」
具体的には、「噛み合わせの悪い人は、なぜか歯が痛くなったり虫歯になったり歯周病になったりしやすい」と感じるのです。
歯並びが悪ければ磨きにくい部分が多くなるので、むし歯ができやすいとも考えられます。歯周病や虫歯などの細菌感染症の立場から考えるならば、確かにそうかもしれません。
しかし、しっかりと歯磨きもできていて、明らかに口腔ケアはきちんとできている方なのに、なぜかいつもトラブルを起こしてダメになってくる人が一定数いるのです。
皆さんの中に、よく磨いているのに、なぜかいつも奥歯に虫歯ができやすくて、銀歯やかぶせ物だらけの方はいませんか?あるいは、特定の場所に歯周病が進んできていて、グラグラの歯が多くなってきている方はいませんか?
噛み合わせが関係しているのでは?
歯並びが悪いということは、言い換えれば噛み合わせが悪いということです。

噛み合わせの良し悪しはどこを見て判断されるのでしょうか。見た目は、噛み合わせの悪さを示す重要な判断基準の一つです。出っ歯など見た目が悪ければ歯並びが悪いと思われるのは当然です。
一方で、前歯のように見えるところではなく、実際に食べ物を噛んだり食事をしたりするときに使うのは圧倒的に奥歯が多いですよね。
噛み合わせが悪いと不自然な噛み方になる
食べ物を口に入れたとき、どこか一カ所でも痛い歯があるとします。
その場合、痛い場所を避けて、別の歯で無理に噛むようになります。
この状態が続くと、顎が疲れてしまいます。
また、他の歯を使いすぎて、今度はそちらが痛くなることもあります。
つまり、どんなに丈夫な歯でも、同じ場所ばかり使うと傷みやすくなります。
噛むときに強く当たる歯や、歯ぎしりが強い歯があると、その歯だけに負担がかかります。これをオーバーロードと言います。
まとめると、歯のトラブルを防ぐには、毎日きれいな口腔内を保つことが大切です。
さらに、歯にかかる力をうまく分散させることも重要です。この2つを意識しましょう。
歯の噛み合わせの強弱のコントロールはどこがしている?
この経験則の正当性をさらに支えてくれそうな論文があります。2020年6月、日本矯正歯科学会の学術奨励賞を受賞した論文です。
https://www.nature.com/articles/s41598-019-44846-4
東京医科歯科大学の矯正学教室と、国立精神神経医療センター、群馬大学医学部の共同研究です。臼歯および前歯咬合時における咀嚼筋活動と脳の活性パターンの差異についての研究データです。
パワーグリップとPrecision grip
人が手で物をつかむとき、力強く握るのをパワーグリップと呼びます。一方、繊細なものに触れる際には、つまんだりなでたりするようにしてつかみます。これをPrecision gripと呼びます。
この2種類の違いを脳が判断して制御しています。奥歯と前歯でも同じように脳の部分で使い分けているのではないかという研究が今回の論文のテーマです。
人は奥歯で物をかみ砕き、前歯はくわえたり、せん断したりしています。その際に、それぞれの働きや制御がどのようにコントロールされているのかは、まだ明らかにされていませんでした。
下の歯と当たっている場合に、前歯の傾き具合が咀嚼運動を制御するという研究は既にありました。
今回の研究では、奥歯での咬合時にはパワーグリップと同様に、強い力で噛むほどに力強く咀嚼する機能が、前歯での咬合時にはPrecision gripと同様に弱い力で噛むほど繊細な運動コントロール機能が作動するという可能性が示唆されました。
つまり、私たちが物を食べる際に運動制御機構は前歯と奥歯とでは異なるということが分かったのです。
噛み合わせごとの違い
噛み合わせが悪い人の代表例として、矯正学的にクラスⅡという分類があります。下の顎が小さく見える感じの人がクラスⅡです。この人たちは奥歯に虫歯が多かったり、かぶせ物が多い傾向があります。
また、顎が強調して見える受け口(クラスⅢ)の人も、奥歯の不調和を訴えることが多いです。両者に共通しているのは、前歯が正常に機能していないことです。
受け口の場合は、どんなに顎を前に動かしても上の歯が後ろにあるため、前歯には当たりません。つまり前歯が機能的に使われないのです。
前歯と奥歯の繊細な連携作業でリズムの取れた適度な噛む力で咀嚼運動する人なら、日頃から各歯牙にかかる力の配分はうまく制御されています。
審美的矯正と機能的矯正
矯正治療は見た目をよくするだけが目的ではありません。
噛むときの力の配分を整えるためにも行います。これが機能的な矯正治療です。
前歯で力をコントロールできない噛み合わせだと、奥歯に大きな力が直接かかります。
必要以上に強い力が続くと、歯がすり減ったり、ひび割れたりします。その結果、虫歯や歯周病にもなりやすくなります。
噛み合わせが悪い方や、矯正治療を希望する方には、顎機能運動精密検査をおすすめしています。
前歯の角度が強すぎても、逆になさすぎても、歯や顎に悪い影響が出ます。
バランスの悪い噛み合わせのまま、インプラントや修復物を入れても、また同じようにトラブルが起きるリスクが残ります。
前歯と奥歯がうまく連携してこそ、咀嚼の力加減が整います。噛みやすく、見た目もきれいになります。
歯列矯正のすすめ
予防歯科は、口の中を清潔に保つだけではありません。
良い噛み合わせを作ることも大切な目的です。
親御さんが早い段階で歯列矯正を考えてくれると、お子さんはとてもラッキーです。
大人になってからでも遅くありません。最近は新しい矯正方法も増え、治療も進化しています。
年齢を重ねて歯を失い、義歯やインプラントにならないためにも、まず噛み合わせを整えることがとても大切です。

歯の治療は、一般的な内科治療などと少し違いがあります。それは「同じ箇所の治療でも、やり方がたくさんある」ということ。例えば、1つの虫歯を治すだけでも「治療方法」「使う材料」「制作方法」がたくさんあります。選択を誤ると、思わぬ苦労や想像していなかった悩みを抱えてしまうことも、少なくありません。
当院では、みなさまに安心と満足の生活を得て頂くことを目標に、皆様の立場に立った治療を心がけています。お気軽にお越し下さい。